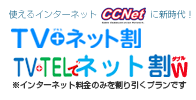≪日本古典への招待≫ 源氏物語物語 前期講座(第1~6回) 後期講座(第7〜12回)

三田村 雅子 国文学者 フェリス女学院大学名誉教授
『源氏物語』は西暦1001年の疫病流行期に新婚間もない夫を喪った未亡人紫式部によって、その虚脱感の中に書かれたと言われています。疫病の最中に書き起こされ、病に脅かされながら書き継がれた作品である『源氏物語』は常に死を前提に置く物語となりました。喪失感の文学です。
死を媒介にした時、愛はどのように維持できるのか。身代わりを求めてしまう心理、満たされない思いなど、死と病と老いという暗い要素とせめぎ合うように生きることの意味、愛の究極が輝きだす瞬間を『源氏物語』の中から12回にわたって読んでいきます。そのことで、源氏物語という大長編のもっとも本質的な部分を理解することができるでしょう。
- 第一回 日本古典への招待『源氏物語』
第一回 疫病の中の『源氏物語』
源氏物語が本格的に書き始められたのは1001年長保三年あたりだと考えられています。その直前わずか四五年のうちに四度の疫病大流行があり、京都の人口の三分の一、高級官僚の半数が亡くなります。紫式部は、その疫病のさ中に物語を書き起こし、疫病の恐怖にうちまかされるのではなく、立ち向かい、その本質を明らかにするような「書かれた世界(物語)」を構築しています。歴史記録や和歌、日記などの資料をもとに、その背景を振り返ってみます。
- 第二回 日本古典への招待『源氏物語』
第二回 物語の始まりと桐壺更衣退出
源氏物語の始まりは、桐壺更衣の死による悲恋の破滅的な終了から語っています。このような不吉な物語の始まり方は珍しいようで、後の時代の人々は、源氏物語を仰ぎ見るように支持していましたが、この不吉な冒頭を嫌って、物語を読み始める時は、初音巻、紅葉賀巻などのめでたい巻から読み始めたようです。室町時代や江戸時代のことです。
それほどまでに衝撃的だった桐壺巻の不吉な語り始めはなぜ必要だったか考えていきましょう。
- 第三回 日本古典への招待『源氏物語』
第三回 廃院の怪異と夕顔の女
桐壺巻では、源氏物語が、身分への強いこだわりを持ち、その身分制度と愛が一致しない場合の葛藤と相克を問題とする作品だということを見てきました。それに続く帚木以下の物語は、光源氏がそれまで体験したことがなかった中の品階級の女との出会いでした。
夕顔との出会いはゆきずりの出会いです。「六条わたりの御忍び歩き」の道すがら、五条夕顔の家五条あたりにあった白い花が咲く粗末な家に心惹かれ、花を一枝所望したところから話は始まります。
- 第四回 日本古典への招待『源氏物語』
第四回 物の気出現と葵上の出産
今回は葵上の懐妊ともののけの出現、そして出産を終えた後の突然の死に至るドラマティックな物語を読んでいきましょう。
光源氏は22歳の大人、すでに大将という重要な役職についています。しかしそれまで彼を支持し、盤石の態勢で支えてきた桐壺帝は退位し、思うようにならない政治の鬱屈を抱え、光源氏は愛人たちに対しても十分な心遣いができなくなります。その結果、六条御息所は光源氏との縁を断つことを考え始めます。
- 第五回 日本古典への招待『源氏物語』
第五回 疫病の中の藤壺崩御
今回は、須磨・明石の沈淪を経て、藤壺所生の冷泉帝即位によって光源氏の政界復帰が叶えられた時期の物語を読んでいきます。病がちの朱雀院が位を皇太子冷泉に譲り、その後見人であった光源氏を大納言に復帰させたのです。
冷泉帝は表向き桐壺院の第十皇子ですが、光源氏と藤壺の秘密の子でしたから、これによって光源氏の権力は他の追随を許さないものに。
しかし冷泉帝が大人の年齢に達したころから藤壺の健康は損なわれていきます。
- 第六回 日本古典への招待『源氏物語』
第六回 不老不死の館
前回は藤壺が亡くなり、その結果、源氏物語が一つの曲がり角を迎えること、これからは光源氏一人でその罪の重さを背負っていかなければならないことが語られました。
そうした転機を迎えた光源氏が、新たに作り上げたのが六条院の世界です。
今回は「生ける仏の御国」とも譬えられた理想的世界、六条院はどのようなものだったのか。光源氏は、そのような世界を作り上げることで、何を成し遂げ、何を排除していったのかについて、考えていきましょう。
- 第七回 光源氏の老い
『源氏物語』は三十三巻目の藤裏葉巻で一つの大団円を迎えます。光源氏は高麗の相人の予言通り、準太上天皇に推戴され、息子夕霧は雲居雁との結婚を許され、娘明石姫君は皇太子に入内し、思い残すことのない栄華が確かめられます。
しかし、物語はさらに書き継がれ、光源氏の後半生、晩年の世界を描いていきます。登場人物の老い、病、死などが次から次へと襲ってきて、生きることの苦痛に満ちた様相を明らかにし、負の側面に舵を切っていくのです
- 第八回 柏木密通と薫誕生
前回は女楽の華やかな場面から一転して紫上が発病し、二条院に移り、光源氏も付き添い六条院ががら空きになった状況を読んできました。光源氏は建前としては女三宮を大事にしていましたが、いざ紫上が発病すると、すべてを忘れて紫上の看病をします。
取り残された女三宮のもとでは琴などもひきこめられ、朱雀院の五十賀も延期に。そこにあの六条院の桜の下の蹴鞠の場面で女三宮を垣間見して以来、忘れることのなかった柏木が近づいてきます。
- 第九回 紫上の病と死をめぐって
光源氏は薫を抱き、その愛らしい無心の瞳に見入ることで、自分と同じような罪を犯した柏木・女三宮も許し、薫も許し、――愚かな行動に走ったかつての自分も、――また許していくのです。――もう一人の主人公薫の物語がここから始まります。
その薫をめぐる物語が本格的に始まる前に、源氏物語は紫上の死という大きな曲がり角を迎えます。もっとも大切な人物として、一貫して愛されてきた紫上の死と光源氏の退場の物語を今回は読んでいきます。
- 第十回 八宮の遺言
光源氏が亡くなり、物語から退場した後、世の中には大きな虚脱感が残り、光源氏を継ぐ人は一人もいなかったと語られます。『源氏物語』はもう、光源氏のような圧倒的な存在、超越的な主人公を求めてはいないのです。わたしたちと同じような、欠点も多く、ちょっとだけ素敵な若者たちをめぐって続編は始まっていきます。
その中で新たなキーパーソンになるのが宇治に住む八宮です。八宮とは何者なのか、なぜ宇治に住むようになったか見ていきましょう。
- 第十一回 宇治大君の病と父の遺言
前回は八宮が相手によって違った感触の遺言を残し、その結果、八宮の真意がどこにあるかが不明であるというお話をいたしました。
今回はその八宮の遺言を額面通り守ろうとする大君と、自分は当然許されていると確信する薫のすれ違い、生活のためには現実を見なければならないという女房たちの経済優先の価値観の違いから、大君が次第に前途を悲観して追い詰められていく過程を読んでいきます。
- 第十二回 浮舟の「死」と再生
大君の看病、その死を看取った薫は、その長い時間を共にした中君に大君思慕の思いを移行していきます。匂宮は、ようやく中君を二条院に迎える許可を得ます。その新居二条院は、薫が大君を迎えようと新築した三条宮の北隣でした。薫は我慢できず、中君に思いを打ち明けます。匂宮の子供を妊娠していた中君は困惑し、薫に「もう一人の妹」を紹介することで危機を回避しようとします。
その「もう一人の妹」こそ、『源氏物語』最後のヒロイン浮舟です。
| 講座名 | ≪日本古典への招待≫ 源氏物語物語 前期講座(第1~6回) 後期講座(第7〜12回) |
|---|---|
| 講師 | 三田村 雅子 フェリス女学院大学名誉教授 |
| 回数 | 全6回 ※本動画はストリーム配信です |
| 期間 | 配信期間:2025年4月1日〜9月30日 受講生には視聴するURLとパスワードをお知らせします。 |
| 開催日 | 配信期間:2025年4月1日〜9月30日 受講生には視聴するURLとパスワードをお知らせします。 |
| 受講料 | 前期:全6回9,900円(税込) 後期:全6回9,900円(税込) |
| 場所 |
山梨文化学園本校 住所:〒400-8545 甲府市北口2-6-10 アネックスⅢ [地図] 電話:055-267-9155 |